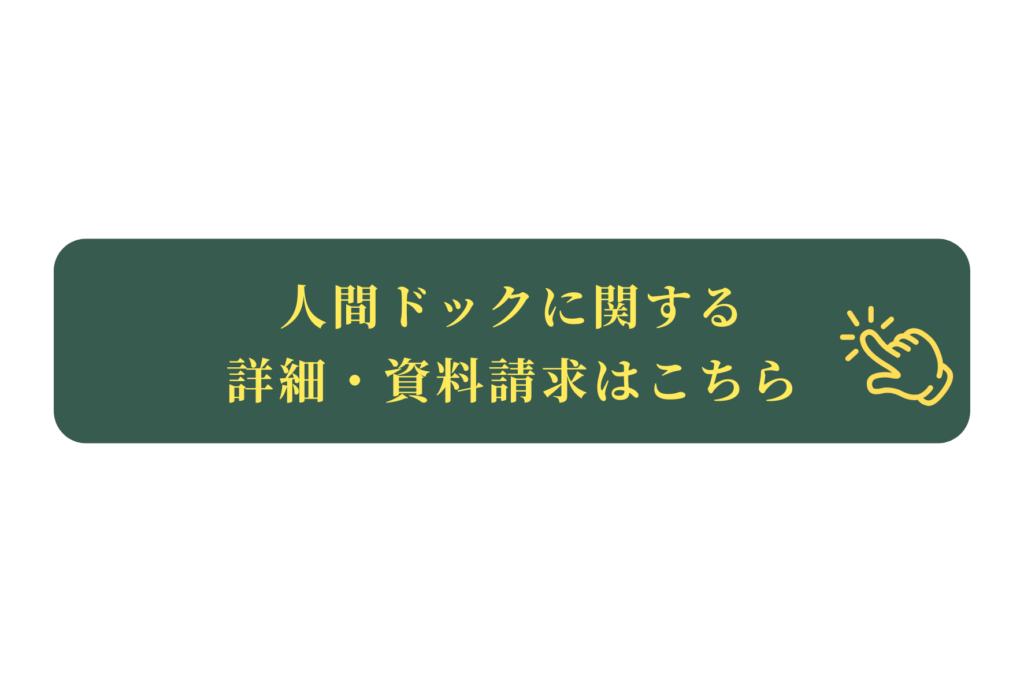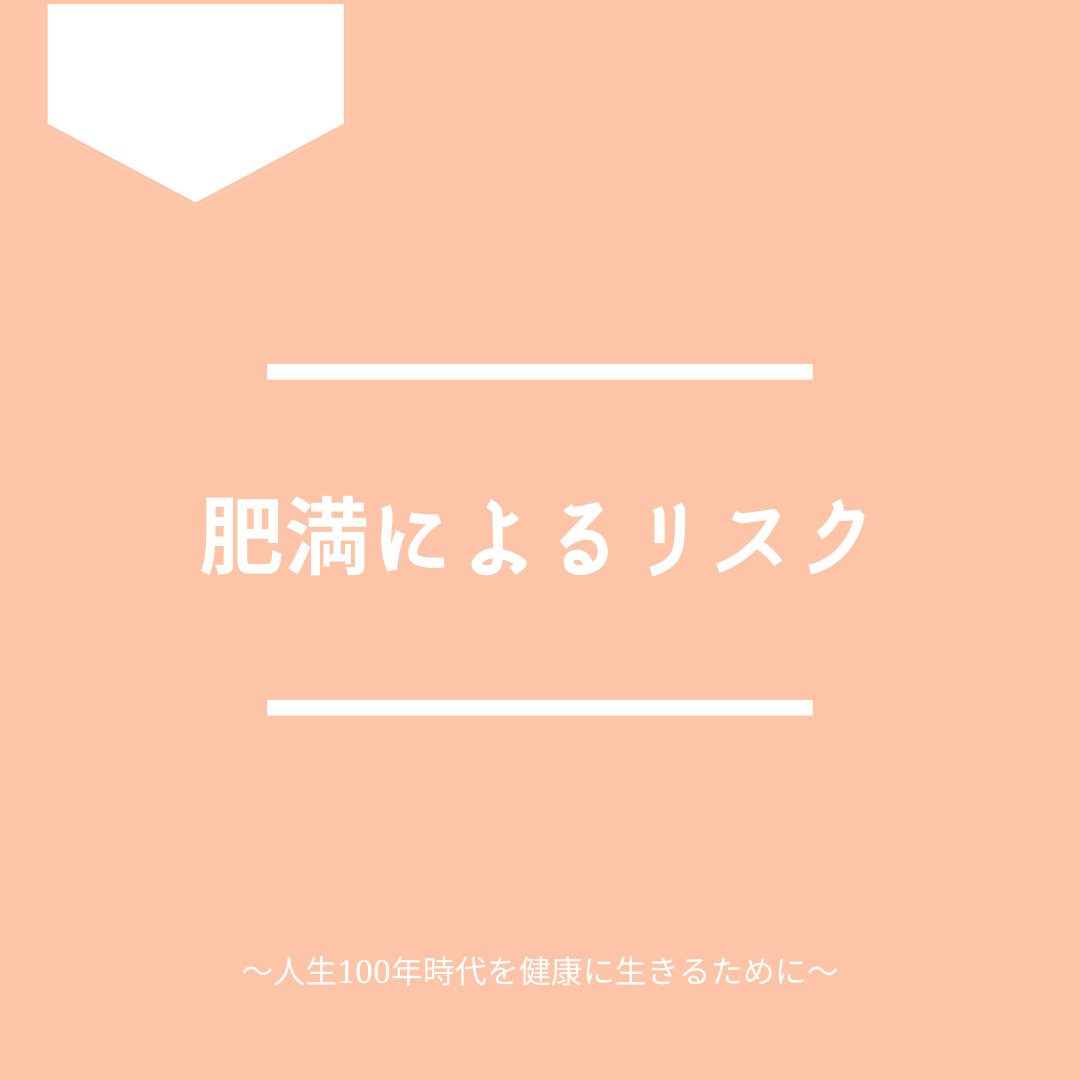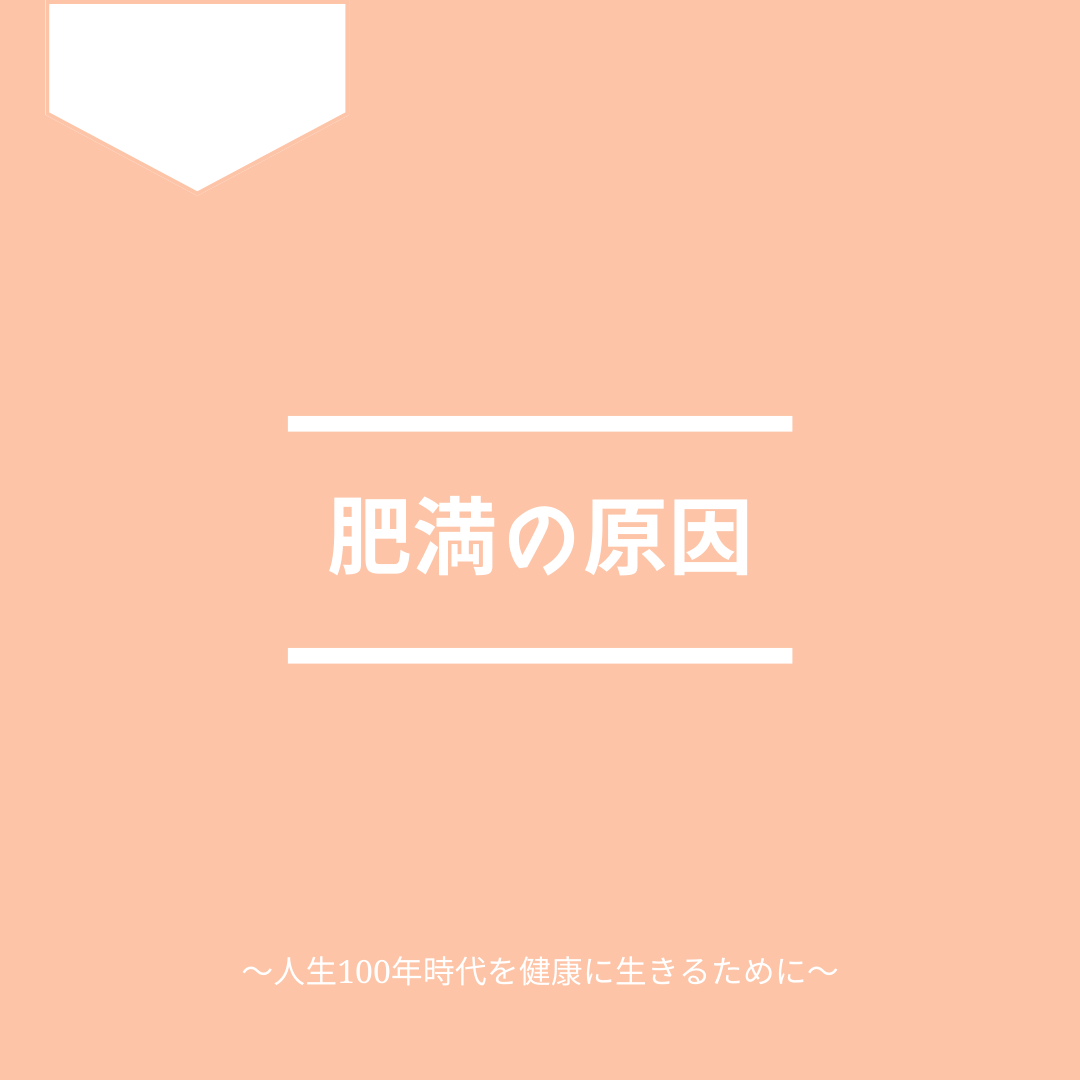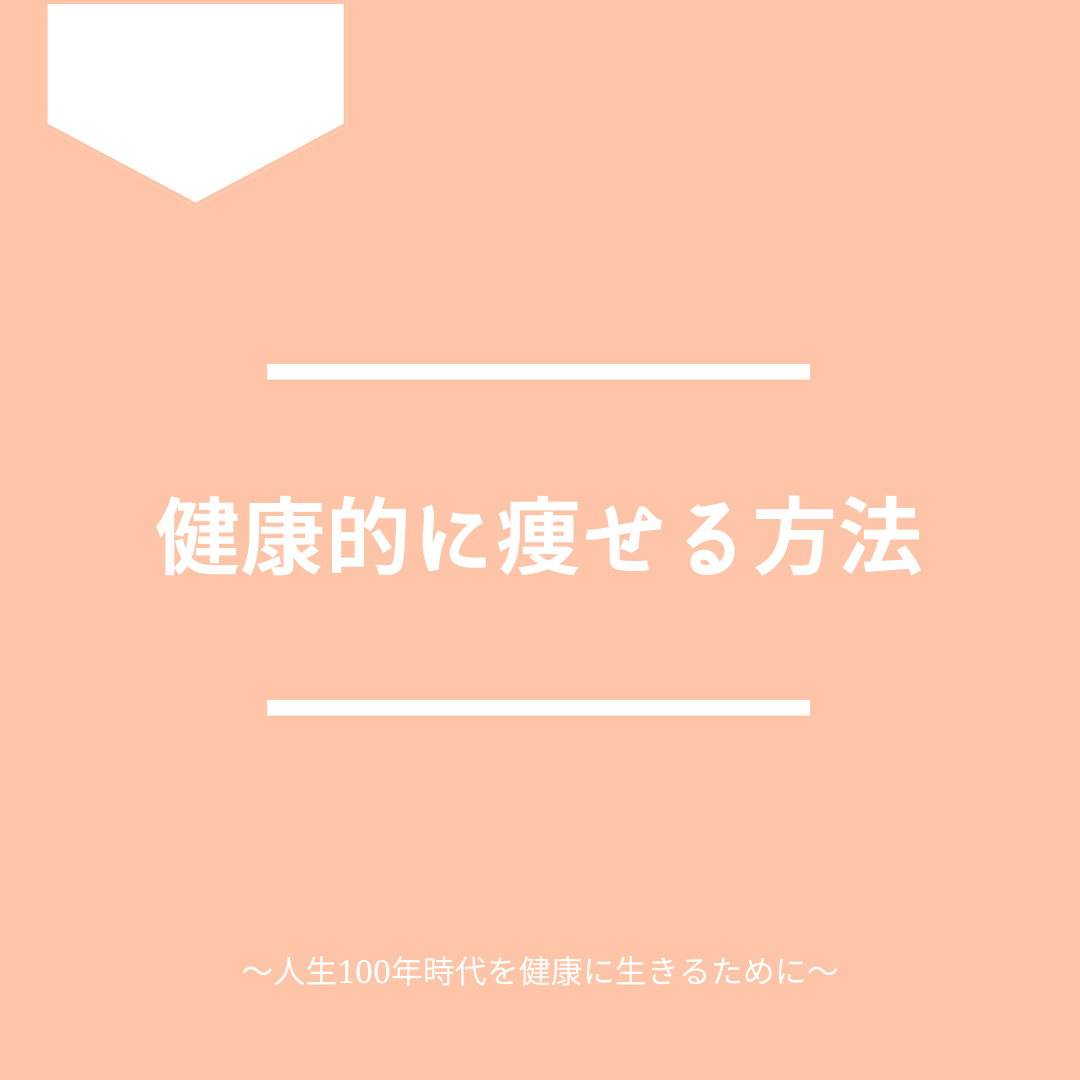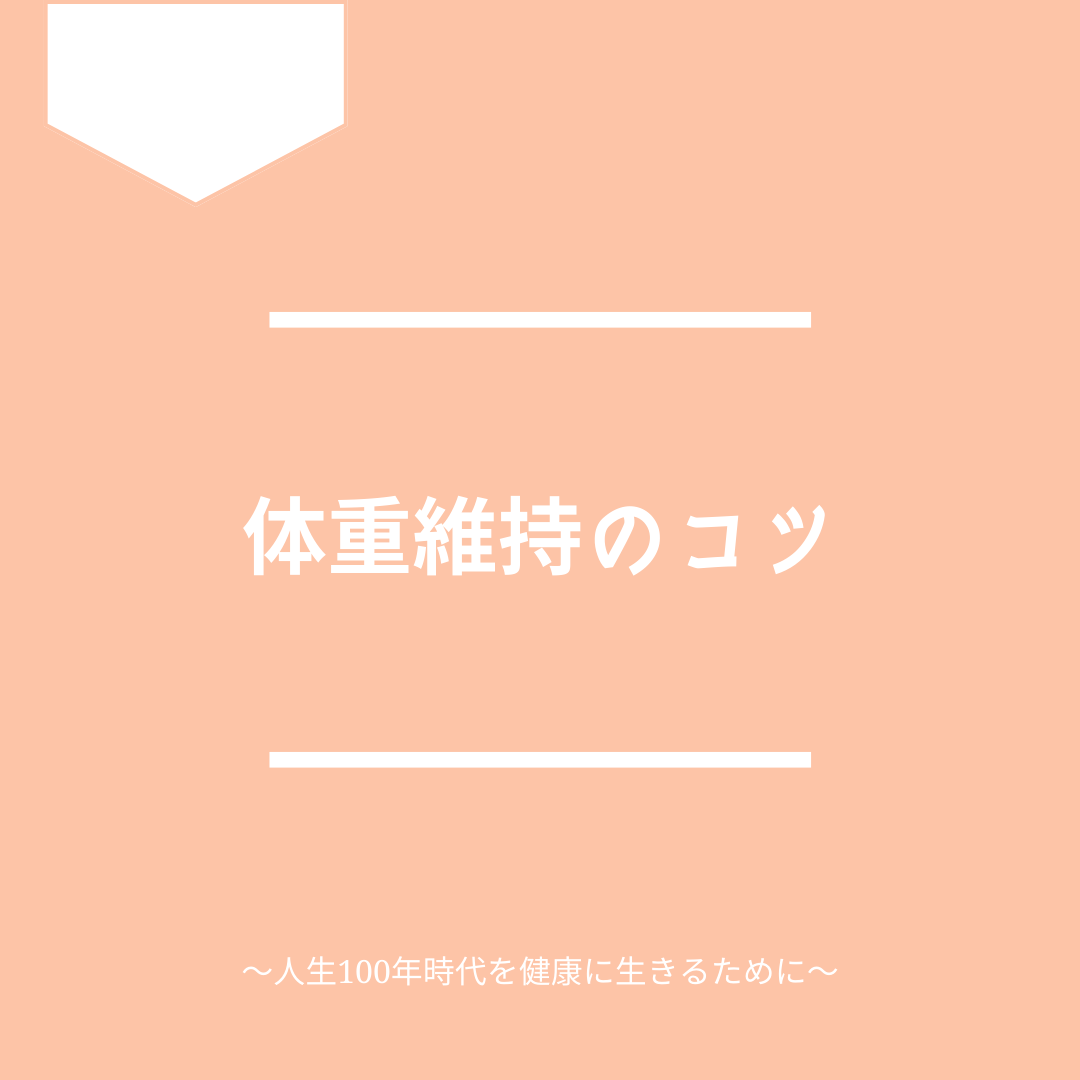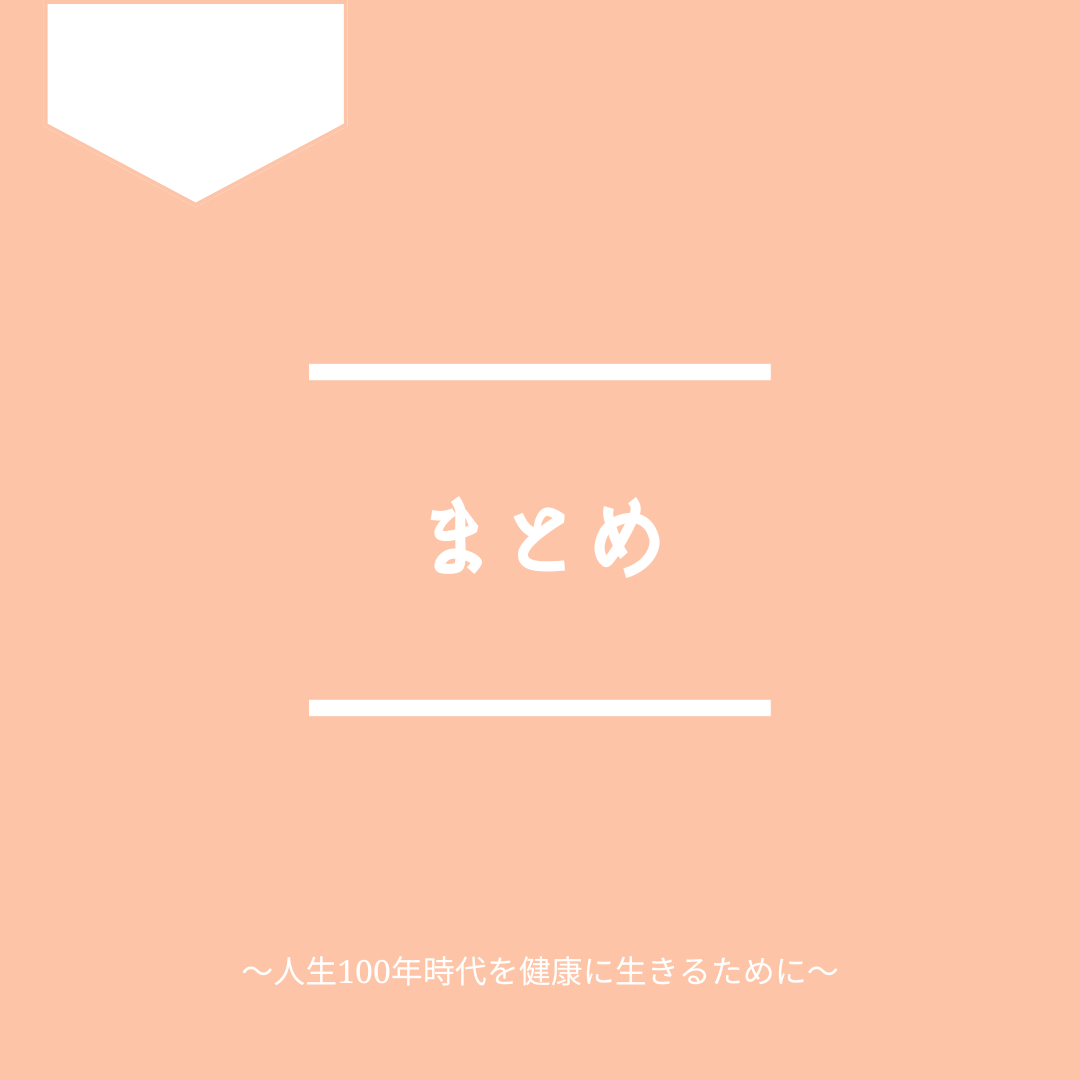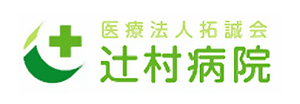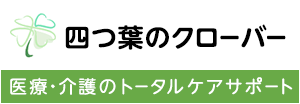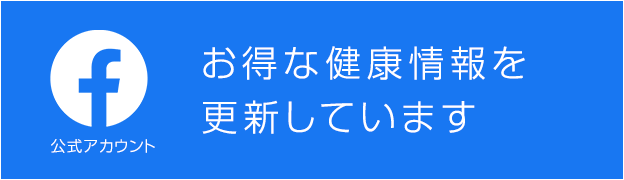肥満が引き起こすリスクと健康的な生活への第一歩
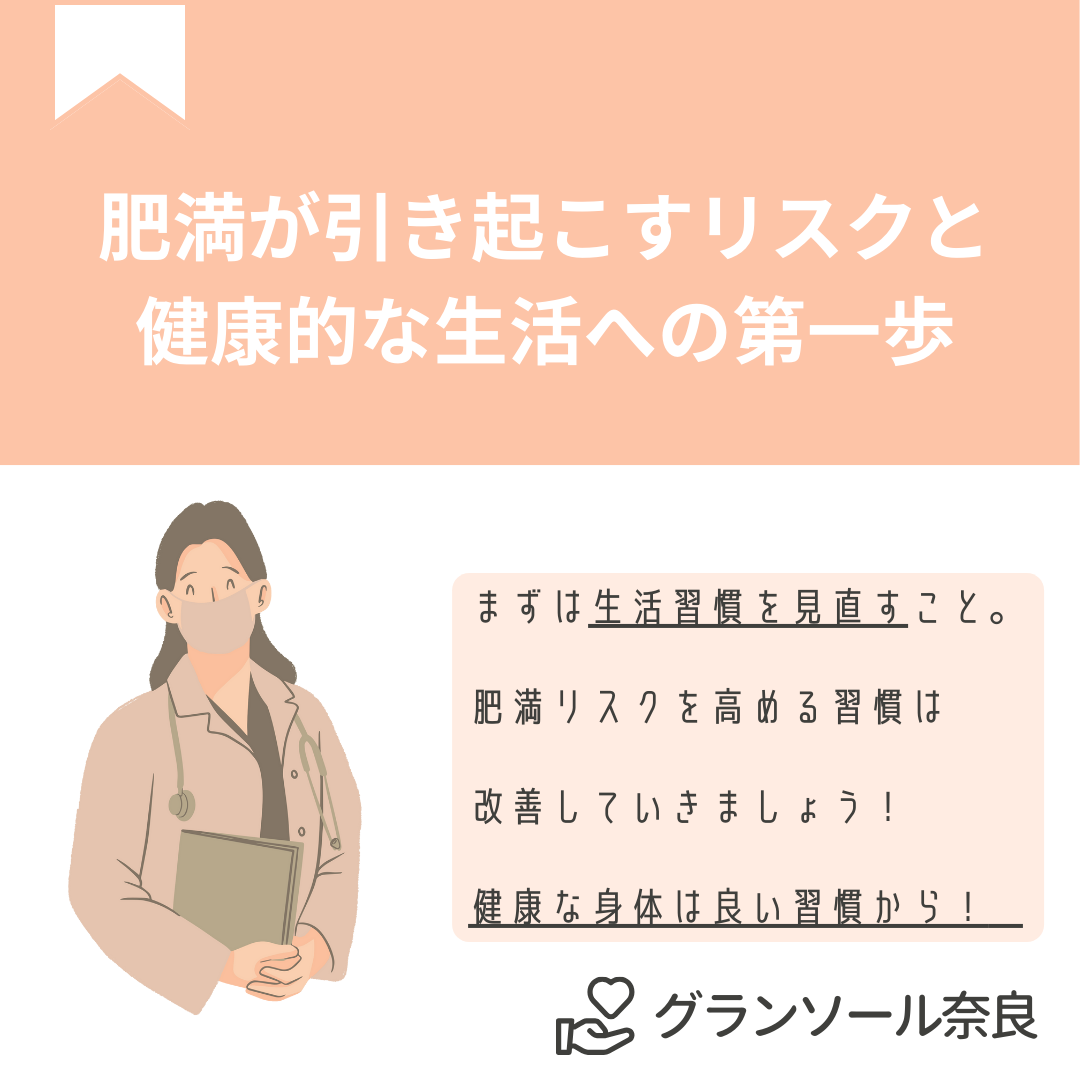
記事の監修
グランソール奈良 院長辻村 貴弘
<経歴>
| 2000年3月 | 奈良県立医科大学大学院薬理学専攻修了 |
|---|---|
| 2001年4月 | グランソール奈良開設 院長に就任 |
| 2005年3月 | 医療法人拓誠会 辻村病院 理事長に就任 |
| 2010年3月 | 京都府立医科大学大学院免疫・微生物学専攻修了 資格:医学博士、日本人間ドック学会認定医 |
近年、日本人の肥満割合が増加傾向にあることが指摘されています。肥満によるリスクは多岐にわたるため、日々の生活習慣を改善し、適切な体重を維持することが大切です。
主な背景としては、次のことが挙げられます。
・食生活の欧米化
・移動手段の発展や働き方の変化による運動不足
・ストレスや生活リズムの乱れ
・加齢に伴う基礎代謝の低下
また、令和5年の厚生労働省が実施した「国民健康・栄養調査」によると、日本人の肥満率は男性31.5%、女性21.1%となっています。
※詳しい調査結果は下記よりご覧ください。
本記事では、肥満の原因や肥満リスクを防ぐために重要なポイントを紹介します。
肥満によるリスク
肥満になると、糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病になるリスクが高まると言われています。
生活習慣病の多くに共通する特徴として、初期の段階では自覚症状がないことも多く、診断時には症状が進行していることがあります。
初期段階で発見し症状の悪化を防ぐためには、定期的に検査を受け、結果に応じた対策を講じることが重要になります。
⇒精密検査を受けるならグランソール奈良
【生活習慣病のリスク】
肥満になると、次のような生活習慣病のリスクが高まります。
・糖尿病(特に2型糖尿病): インスリン抵抗性が高まり、血糖値が上昇しやすくなります。
・高血圧: 体重増加に伴い心臓や血管への負担が増加します。
・脂質異常症: 血中のコレステロールや中性脂肪が増え、動脈硬化のリスクが高まります。
・一部のがん(乳がん、大腸がん、肝臓がんなど)の発症リスクが高まることが研究で示されています。
【精神的健康】
肥満リスクは精神的な面でも起こり得ます。
例えば、肥満による見た目の変化は自己評価の低下やうつ病のリスクを高める可能性があります。
特に、年齢を重ねると肌のたるみや筋肉量の低下と相まって、体型の変化が目立つようになります。
また、若い頃に効果的だったダイエット法が通用しなくなることもあります。
【肥満による関節や呼吸器への影響】
体重増加は膝や腰などの関節に負担をかけ、関節炎や関節痛の原因となることがあります。
特に40代以降は、運動不足による筋肉量の減少や体脂肪の増加が加わり、そのリスクが高まります。
一度、関節炎や関節痛を引き起こすと、さらに運動の機会が減少するため悪循環に陥ることもあります。
また、睡眠時無呼吸症候群(SAS)のリスクが高まり、睡眠の質が低下します。
【妊娠や生殖機能への影響】
妊娠中の過剰な体重増加は、妊娠糖尿病や妊娠高血圧症候群、血栓症のリスクを高めます。
出産時のリスクとしては、帝王切開や手術後の合併症になる可能性が高まると言われています。
さらには、胎児への影響として巨大児(マクロソミア)や先天性異常のリスク増加、長期的な健康リスク増加などの可能性が高まります。
肥満になる原因
肥満の原因は人によってさまざまです。
基本的には、摂取カロリーが消費カロリーを上回ることで体重は増加します。
しかし、他にもさまざまな要因があるため以下で詳しく紹介します。
まずは体重増加の原因を知り、その要因を取り除くことが大切です。
【不適切な食生活による肥満】
食べ過ぎによる余分なエネルギーは脂肪として蓄積されます。
そして、蓄積された脂肪が肥満の原因となります。
特に、高カロリー食品や加工食品、砂糖を多く含む飲み物の過剰摂取は体重増加に大きく影響します。
さらに、高脂質や高糖質で栄養バランスが偏ると肥満のリスクが高まります。また、夜遅くに食べると消化が不十分になり、体脂肪として蓄積されやすくなります。
加えて、小腹が空いたときの間食やストレスによる過食も体重増加の要因となります。
【加齢による筋力や基礎代謝の低下】
筋力の低下は40代以降から徐々に進行し、60代以降で顕著となります。
主な原因としては、加齢による筋肉量の減少です。(=サルコペニア)
筋肉量の減少と同様に基礎代謝も低下します。
そのため、若い頃と同じ食事量や運動量では体重が増加します。
従って、肥満になる可能性も高まります。
【更年期やホルモンバランスの乱れ】
女性の場合、更年期による影響も考えられます。
例えば、更年期にはエストロゲンが減少すると言われています。
エストロゲンの役割には、食欲の抑制や代謝の調整があります。
つまり、エストロゲンが減少すると体重増加の可能性が高まります。
男性の場合も更年期による影響は考えられます。
男性更年期障害は男性ホルモン(テストステロン)の減少によって起こります。
テストステロンの役割には、筋肉量の増加を促す働きがあります。
つまり、テストステロンが減少すると筋肉量が低下し、内臓脂肪の増加につながります。
【運動不足や睡眠不足による肥満】
運動不足や睡眠不足は体重増加につながる可能性が高いです。
例えば、デスクワークや車での移動が多い方は日常生活で運動量が少なく、消費カロリーが減少します。
そして、睡眠不足は空腹感を増加させる「グレリン」の分泌を増やします。
一方で、満腹感を感じる「レプチン」を減少させるため、食べ過ぎを招く可能性があります。
加えて、睡眠不足によりエネルギー不足を感じ活動量が減少します。
【ストレスや薬の副作用】
ストレスによるコルチゾールの過剰分泌も肥満になる原因の一つです。
コルチゾールとは、ストレスに対処するためのホルモンで”ストレスホルモン”とも呼ばれます。
コルチゾールの役割には、糖新生や脂肪分解などがあります。
生体にとっては必須ホルモンである一方、過剰分泌は健康リスクが高まります。
その一つに、過剰な空腹感による体重増加が挙げられます。
また、抗うつ薬やステロイド薬、糖尿病薬など、一部の薬は副作用として体重増加を引き起こすことがあります。
その際は、かかりつけ医に相談しましょう。
健康的に痩せる方法
健康的な身体を手に入れるために、過度なダイエットは控えましょう。
過度なダイエットより、ホルモンバランスを意識しつつ、バランスの取れた食事や適度な運動、ストレスケアを取り入れることが重要になります。
また、体重管理も重要な習慣です。
体重管理は見た目だけでなく、健康維持や生活の質に直結すると考えられています。
定期的に体の変化を測ることにより、モチベーションアップや自分に合った体重管理の方法を見つけることに繋がります。
⇒精密検査を受けるならグランソール奈良
【バランスの良い食事】
- 栄養素のバランスを重視
☞主食(炭水化物)、主菜(タンパク質)、副菜(野菜)を組み合わせた食事をとる。
加工食品や砂糖を多く含む食品は控えめに。
- 食物繊維を摂取
☞野菜、果物、全粒穀物、豆類を積極的に摂ることで満腹感を得やすくなり、
血糖値の急上昇を防ぎます。
- 間食をヘルシーに
☞ナッツやヨーグルト、果物などを選ぶ。
【適度な運動で肥満リスクを回避】
いきなり激しい運動をすると怪我等のリスクがある為、まずは次のような運動を推奨します。
- 有酸素運動
⇒ウォーキング、ランニング、水泳、サイクリングなどを週に3〜5日、30〜60分程度行う。 - 筋力トレーニング
⇒筋肉量を増やすことで基礎代謝を高め、脂肪を燃焼しやすい体を作る。 - 日常生活での活動を増やす
⇒階段を使う、通勤で歩くなど、日常の小さな運動を増やす。
【食事の習慣を見直す】
いわゆる「早食い」をしていると、食べすぎや胃腸への負担が増えるなどのマイナス要因があります。
一口ずつしっかり噛む・ゆっくり食べることで満腹感を感じやすくなります。
また、規則正しい時間に食べることで血糖値の乱れを防ぎ、過食を予防できます。
【ストレス管理と睡眠】
近年の日本では、ストレスを感じる人が増加していると言われています。
前述したように、ストレスは過食などを引き起こす原因となります。
ストレスを溜めない工夫として、ヨガや瞑想、趣味の時間を持つなど、リラックスできる方法を見つけることが大切です。
また、質の良い十分な睡眠(7〜8時間)を確保することでホルモンバランスを調整することができます。
体重維持のコツ
適切な体重を維持するために大切なことはいくつかあります。
一般的に言われるのは「バランスの取れた食事」や「適度な運動」、「十分な睡眠」です。
他にも、ストレス解消や定期的な検査の受診などがあります。
何より、これらを継続して行うことが重要です。
継続するためのコツとして、次のことが挙げられます。
・過度な食事制限をしない
・一人ではなく誰かと共有して行うこと
・日々の食事や体重を目に見える形で記録する
自分なりに工夫して、良質な健康習慣を手に入れましょう!
【持続可能な生活習慣を手に入れる】
適切な体重を長く維持するためには、短期間の極端なダイエットではなく続けられる習慣を取り入れることが大切です。
急激に減量した場合はリバウンドしやすいので、徐々に減らすことを意識しましょう。
そもそも肥満と肥満症は定義が異なります。
肥満の方はBMI値を正常値に近づけることを目標にすると良いです。
しかし、肥満症の方はBMI値だけでなく内臓脂肪を減らすことが重要になります。
*肥満と肥満症の違い等に関する詳細は下記をご参考ください。
<参考文献>
日本肥満学会編「肥満症診療ガイドライン2016」ライフサイエンス出版, 2016.
【体重管理を習慣化】
体重管理を習慣化するためには、「毎日」または「週に数回」体重を測定し、目に見える形で増減を把握することが重要です。
その際、できるだけ同じ時間(条件下)に測定することを意識しましょう。
また、増加の兆候があればできる限り早めに対処しましょう。
【生活環境を整えて肥満を予防】
健康的な食品を常備し、高カロリーな食品を家に置かないようにしましょう。
また、テレビやスマホを見ながらの食事が習慣化している方は、食事に集中することを意識しましょう。
たくさん噛んで(1口30回以上)ゆっくり食べることで満腹感を得られ、過食を防ぐことに繋がります。
【社会的サポートを活用】
一人で頑張ろうとすると続かないことが多いですが、
家族や友人と一緒に健康的な目標を共有することで継続につながります。
必要に応じて医師や保健師・管理栄養士に相談することも、一つの手段としては良いかもしれませんね!
<注意点>
過度な食事制限や高負荷な運動は、体への負担が大きすぎて逆効果になることがあります。
体重だけにこだわらず、体脂肪率や筋肉量などもチェックすることが大切です。
急激な体重減少は悪影響を及ぼす可能性があるため注意しましょう。
まとめ
肥満になると糖尿病や高血圧、脂質異常症など生活習慣病のリスクが高まります。
また、見た目の変化による自己評価の低下やうつ病のリスクを高める可能性もあります。
肥満のリスクを回避するためには、
「バランスの取れた食生活」「適度な運動」「ストレス管理」「十分な睡眠」が重要です。
健康的な体を手に入れるためには”日々の小さな積み重ね”が大切です。
まずは「1日プラス10分の散歩」や「よく噛んでゆっくり食べる」など、取り組みやすいことから始めましょう!
また、急激な体重増加がある場合や自己管理が難しい場合は、医師や保健師・管理栄養士に相談することをおすすめします。
※参考文献(2025年4月18日 現在)
全国健康保険協会 協会けんぽ「健康サポート」3月 よく噛んで、ずっと元気に!
日本肥満学会編「肥満症診療ガイドライン2016」ライフサイエンス出版, 2016.